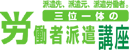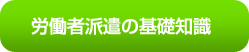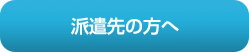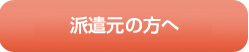2-2-1 派遣先均等・均衡方式における派遣労働者の待遇ごとの具体例
派遣先均等・均衡方式において、派遣労働者に対する待遇と派遣先に雇用される労働者との間の待遇差が、不合理な待遇差として問題となるか否かの判断は、ケースごとに待遇の内容等が考量され、総合的な判断が必要です。労使協定方式(以下2-3参照)と比べて、判断が難しいといえます。
以下は、ガイドライン掲載の例を参考に解説していますが、わかりやすくするために基本的な事例を設定していますので、個々の事例ごとに事情が異なれば結論が変わる可能性もあることを付言しておきます。
以下次のように表示します。
- 派遣先A会社=先
- 派遣元B会社=元
- 派遣先A会社で雇用されている通常の労働者X=X
- 派遣先A会社で雇用されている通常の労働者Z(Xとは責任の程度等働き方が異なる)=Z
- 派遣元B会社から派遣先A会社に派遣されている派遣労働者Y=Y
- 派遣元B会社から派遣先A会社に派遣されている派遣労働者W(Yとは所定労働日数等働き方が異なる)=W
問題となる例には★をつけています。
①基本給1…労働者の能力又は経験に応じて支給するもの
例1(均衡待遇の例…能力に違いがある場合)
先は、ある能力の向上のための特殊なキャリアコースを設定しています。Xは、このキャリアコースを選択し、その結果としてその能力を習得したため、先はその能力に応じた基本給をXに支給しています。これに対し、元から先に派遣されているYは、その能力を習得していないため、元はその能力に応じた基本給をYには支給していません。
(筆者コメント:「特殊なキャリアコース」という限定がついた事例です。派遣元事業主も派遣先も派遣労働者のキャリア形成に努めるべきことは、当然です(派遣元の方へ Q18、Q19参照)。
例2(均衡待遇の例…キャリアコースに違いがある場合)
先において定期的に職務の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者の総合職であるXは、管理職となるためのキャリアコースの一環として、新卒採用後の数年間、店舗等において、職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者であるYの助言を受けながら、Yと同様の定型的な業務に従事しています。元はYに対し、当該定型的な業務における能力又は経験はXを上回っているものの、Xに比べ低い基本給を支給しています。
(筆者コメント:XとYとの具体的な基本給額の相違が大きい場合には、不合理な待遇差と認められる可能性があると考えます。)
例3(均衡待遇の例…勤務地変更の有無に違いがある場合)
過去に有期雇用労働者であったXは、能力又は経験が一定の水準を満たしたため、先はXを定期的に職務の内容及び勤務地に変更がある通常の労働者として登用しています。Xは、元から先に派遣されているYと同一の職場で同一の業務に従事しています。元は、先で就業する間は職務の内容及び勤務地に変更がないことを理由に、Yに対して、Xほど基本給を高く支給していません。
(筆者コメント:XとYとの具体的な基本給額の相違が大きい場合には、不合理な待遇差と認められる可能性があると考えます。)
例4(均衡待遇の例…就業の時間帯や就業日等に違いがある場合)
XとYは同一の能力又は経験を有しています。元は、先がXに適用する基準と同一の基準をYに適用し、就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は休日か否か等の違いにより、先がXに支給する時間当たりの基本給との間に差を設けています。
(筆者コメント:労働者の採用が難しい時間帯や曜日、休日に勤務する場合に基本給を高めに設定するのは不合理な待遇差ではありません。)
★例5(不合理な待遇差と認められる例…「経験」が業務と関連性がない場合)
先及び元は、基本給について労働者の能力又は経験に応じて支給しています。元はYに対し、Xに比べて経験が少ないことを理由として、先がXに支給するほど基本給を高く支給していません。しかし、Xのこれまでの経験はXの現在の業務に関連性を持っていません。
②基本給2…労働者の業績又は成果に応じて支給するもの
例6(均衡待遇の例…業績又は成果に違いがある場合)
先及び元は、基本給の一部について労働者の業績又は成果に応じて支給しています。元は、所定労働時間がXの半分であるYに対し、その販売実績が先に雇用される通常の労働者に設定されている販売目標の半分の数値に達した場合には、先に雇用される通常の労働者が販売目標を達成した場合の半分を支給しています。
例7(均衡待遇の例…責任の有無に違いがある場合)
XとYは、同様の業務に従事していますが、Xは先における生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っており、当該目標値を達成していない場合、待遇上の不利益を課されています。その一方で、Yは、先における生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っておらず、当該目標値を達成していない場合にも、待遇上の不利益を課されていません。元はYに対し、待遇上の不利益を課していないこととの見合いに応じて、先がXに支給するほど基本給を高く支給していません。
★例8(問題となる例…業績又は成果に違いがある場合)
先及び元においては、基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているところ、元は、所定労働時間がXの半分であるYに対し、Xが販売目標を達成した場合に先が行っている支給を、YについてXと同一の販売目標を設定し、それを達成しない場合には行っていません。
(筆者コメント:派遣元事業主は、例6のような対応をすべきです。)
③基本給3…労働者の勤続年数(派遣労働者にあっては、当該派遣先における就業期間)応じて支給するもの
例9(均衡待遇の例…勤続年数、就業期間に違いがある場合)
先及び元は、基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しているところ、元はYに対し、先への労働者派遣の開始時から通算して就業期間を評価した上で基本給を支給しています。
★例10(問題となる例…派遣労働者について就業期間を通算していない場合)
先及び元は、基本給について労働者の勤続年数に応じて支給しているところ、期間の定めのある労働者派遣契約を更新しているYに対し、Yの先への労働者派遣の開始時から通算して就業期間を評価せず、その時点の労働者派遣契約に基づく派遣就業の期間のみにより就業期間を評価した上で基本給を支給しています。
④基本給4…昇給を労働者の勤続(派遣労働者にあっては、当該派遣先における就業の継続)による能力の向上に応じて行うもの
例11(均等待遇の例…能力の向上が同じである場合)
先及び元は、昇給について、労働者の勤続による能力の向上に応じて行っているところ、元は、Xと同様に勤続により能力が向上したYに対し、勤続により能力の向上に応じた部分について、Xと同一の昇給をしています。
★例12(問題となる例…派遣労働者について能力の向上を評価していない場合)
先及び元は、昇給について、労働者の勤続による能力の向上に応じて行っているところ、元は、Xと同様に勤続により能力が向上したYに対し、昇給を全くしていません。
⑤賞与…会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するもの
例13(均等待遇の例…同一の貢献がある場合)
先及び元においては、賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給しているところ、元は、Xと同一の先の業績等への貢献があるYに対して、先がXに支給するのと同一の賞与を支給しています。
例14(均衡待遇の例…生産効率及び品質の目標値に対する責任の有無に違いがある場合)
Xは、先における生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っており、当該目標値を達成していない場合、待遇上の不利益を課されています。その一方で、先に雇用される通常の労働者であるZや、先に派遣されているYは、先における生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っておらず、当該目標値を達成していない場合にも、待遇上の不利益を課されていません。先はXに対して賞与を支給しているが、Zに対しては、待遇上の不利益を課していないこととの見合いの範囲内で賞与を支給していないところ、元はYに対して、待遇上の不利益を課していないこととの見合いの範囲内で賞与を支給していません。
(筆者コメント:派遣先の通常の労働者に、責任があるが賞与を支給されているXと責任はないが支給されていないZがおり、責任のない派遣労働者であるYが、責任のないZと同一の=賞与を支給されていない場合です。)
★例15(問題となる例…貢献がある派遣労働者に賞与を支給していない場合)
先及び元は、賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給していますが、Xと同一の先の業績等への貢献があるYに対して、先がXに支給するのと同一の賞与を支給していません。
★例16(問題となる例…派遣先が貢献の有無にかかわらず何らかの賞与を支給しているのに、派遣元事業主は派遣労働者には支給していない場合)
賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給している先においては、通常の労働者の全員に職務の内容や会社の業績等への貢献等にかかわらず何らかの賞与を支給していますが、元においては、派遣労働者Yに対し賞与を支給していません。
⑥手当1…役職手当=役職の内容に対して支給する手当
例17(均等待遇の例…同一の役職名で同一の内容の役職に対し同一の役職手当を支給している場合)
先および元においては、役職手当について、役職の内容に対して支給しているところ、元は、先のXの役職と同一の役職名(例えば、店長)であって同一の内容(例えば、営業時間中の店舗の適切な運営)の役職に就くYに対し、先がXに支給するのと同一の役職手当を支給しています。
例18(均衡待遇の例…所定労働時間に比例した役職手当を支給している場合)
先および元においては、役職手当について、役職の内容に対して支給しているところ、元は、Xの役職と同一の役職名であって同一の内容の役職に就くYに、所定労働時間に比例した役職手当(例えば、所定労働時間が先に雇用される通常の労働者の半分の派遣労働者にあっては、当該通常の労働者の半分の役職手当)を支給しています。
★例19(問題となる例…同一の役職名で同一の内容の役職に対し派遣元が低い役職手当を支給している場合)
先および元においては、役職手当について役職の内容に対して支給していますが、元は、Xの役職と同一の役職名であって同一の内容の役職に就くYに対し、先がXに支給するのに比べ役職手当を低く支給しています。
⑦手当2…特殊作業手当=業務の危険度又は作業環境に応じて支給する手当
派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の危険度又は作業環境の業務に従事する派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の特殊作業手当を支給しなければなりません。
⑧手当3…交替制勤務等の勤務形態に応じて支給される特殊勤務手当
例20(均衡待遇の例…就業する時間帯等を特定しているか否かの違いがある場合)
先においては、就業する時間帯又は曜日を特定して就業する通常の労働者Xには労働者の採用が難しい早朝若しくは深夜又は土日祝日に就業する場合に時給に上乗せして特殊勤務手当を支給しますが、就業する時間帯及び曜日を特定していない通常の労働者Zには労働者の採用が難しい時間帯又は曜日に勤務する場合であっても時給に上乗せして特殊勤務手当を支給していません。元は、派遣労働者であって、就業する時間帯及び曜日を特定して就業していないYに対し、採用が難しい時間帯や曜日に勤務する場合であっても時給に上乗せして特殊勤務手当を支給していません。
(筆者コメント:派遣先の通常の労働者に、就業する時間帯等を特定しているXと特定していないZがおり、特定していない派遣労働者のYが、特定していないZと同一の=特殊勤務手当を支給されていない場合です。)
例21(均等待遇の例…基本給に特殊勤務手当分が含まれている場合)
先においては、通常の労働者であるXについては、入社に当たり交替制勤務に従事することは必ずしも確定しておらず、業務の繁閑等生産の都合に応じて通常勤務又は交替制勤務のいずれにも従事する可能性があり、交替制勤務に従事した場合に限り特殊勤務手当が支給されています。
Yについては、労働者派遣に当たり先で交替制勤務に従事することを明確にし、かつ、基本給に先において通常の労働者Xに支給される特殊勤務手当と同一の交替制勤務の負荷分が盛り込まれています。先には、職務の内容がYと同一であり通常勤務のみに従事することが予定され、実際に通常勤務のみに従事する労働者であるZがいるところ、元はYに対し、先がZに対して支給するのに比べ基本給を高く支給しています。先はXに対して特殊勤務手当を支給していますが、元はYに対して特殊勤務手当という名称では手当を支給していません。
(筆者コメント:特殊勤務手当という名称では支給をしていませんが、実質的にYは、特殊勤務手当分を盛り込んだ基本給を取得している例です。)
⑨手当4…精皆勤手当
派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者と業務の内容が同一の派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の精皆勤手当を支給しなければなりません。
例22(均衡待遇の例…欠勤についてマイナス査定を行っているか否かの違いがある場合)
先においては、考課上、欠勤についてマイナス査定を行い、かつ、それが待遇に反映される通常の労働者であるXには、一定の日数以上出勤した場合に精皆勤手当を支給していますが、元は、派遣労働者であって、考課上、欠勤についてマイナス査定を行っていないYには、マイナス査定を行っていないこととの見合いの範囲内で、精皆勤手当を支給していません。
⑩手当5…時間外労働に対して支給される手当
派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者の所定労働時間を超えて、当該通常の労働者と同一の時間外労働を行った派遣労働者には、当該通常の労働者の所定労働時間を超えた時間につき、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の割増率等で、時間外労働に対して支給される手当を支給しなければなりません。
⑪手当6…深夜労働又は休日労働に対して支給される手当
派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の深夜労働又は休日労働を行った派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の割増率等で、深夜労働又は休日労働に対して支給される手当を支給しなければなりません。
例23(均等待遇の例)
元においては、先に雇用される通常の労働者であるXと時間数及び職務の内容が同一の深夜労働又は休日労働を行ったYに対し、先がXに支給するのと同一の深夜労働又は休日労働に対して支給される手当を支給しています。
★例24(問題となる例)
Xと時間数及び職務の内容が同一の深夜労働又は休日労働を行ったYに対し、元はYが派遣労働者であることから、深夜労働又は休日労働に対して支給される手当の単価をXより低く設定しています。
⑫手当7…通勤手当及び出張旅費
派遣元事業主は、派遣労働者にも、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の通勤手当及び出張旅費を支給しなければなりません。
例25(均衡待遇の例…通勤手当の上限の有無に違いがある場合)
先は、本社の採用である通常の労働者に対し、交通費実費の全額に相当する通勤手当を支給していますが、元は、元のそれぞれの店舗の採用である労働者については、当該店舗の近隣から通うことができる交通費に相当する額に通勤手当の上限を設定して当該上限の額の範囲内で通勤手当を支給しています。元の店舗採用であって先に派遣されているYが、先への労働者派遣の開始後、本人の都合で通勤手当の上限の額では通うことができないところへ転居してなお通い続けている場合について、元は当該上限の額の範囲内で通勤手当を支給しています。
(筆者コメント:店舗採用の派遣労働者が、本人の都合で転居した事例です。)
例26(均衡待遇の例…所定労働日数等に違いがある場合)
先は、通勤手当について所定労働日数が多い(例えば、週4日以上)通常の労働者Xに月額の定期券の金額に相当する額を支給していますが、元は、所定労働日数が少ない(例えば、週3日以下)又は出勤日数が変動する派遣労働者Yに、日額の交通費に相当する額を支給しています。
★例27(問題となる例)
先は、通常の労働者Xに対し、交通費実費の全額に相当する通勤手当を支給していますが、元はYが派遣労働者であることを理由に通勤手当を支給していません。
⑬手当8…食事手当=労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働者に対する食費の負担補助として支給される手当
派遣元事業主は、派遣労働者にも、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の食事手当を支給しなければなりません。
例28(均衡待遇の例…昼食のための休憩時間の有無に違いがある場合)
先においては、その労働時間の途中に昼食のための休憩時間があるXに食事手当を支給しています。その一方で、元においてはその労働時間の途中に昼食のための休憩時間がない(例えば、午後2時から午後5時までの勤務)Yに食事手当を支給していません。
★例29(問題となる例)
先においてXに食事手当を支給しています。しかし元は、Yに、先がXに支給するのに比べ食事手当を低く支給していません。
⑭手当9…単身赴任手当
派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の支給要件を満たす派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の単身赴任手当を支給しなければなりません。
⑮手当10…地域手当=特定の地域で働く労働者に対する補償として支給される地域手当
派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の地域で働く派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の地域手当を支給しなければなりません。
例30(均等待遇の例)
先においては、Xについて全国一律の基本給の体系を適用し、転勤があることから地域の物価等を勘案した地域手当を支給しています。一方で、元においては、Yについては、先に派遣されている間は勤務地の変更がなく、その派遣先の所在する地域で基本給を設定しており、その中で地域の物価が基本給に盛り込まれているため、地域手当を支給していません。
★例31(問題となる例)
Xは、その地域で採用され転勤はないにもかかわらず、先はXに対し地域手当を支給しています。一方、Yは、先に派遣されている間転勤はありませんが、元はYに対し地域手当を支給していません。
⑯福利厚生1…福利厚生施設(給食施設、休憩室及び更衣室のこと)
派遣先は、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の事業所で働く派遣労働者に、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の福利厚生施設の利用を認めなければなりません。また派遣元事業主についても、労働者派遣法第30条の3(不合理な待遇の禁止等)の規定に基づく義務を免れるものではありません。
⑰福利厚生2…転勤者用社宅
派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の支給要件(例えば、転勤の有無、扶養家族の有無、住宅の賃貸又は収入の額)を満たす派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の転勤者用社宅の利用を認めなければなりません。
⑱福利厚生3…慶弔休暇並びに健康診断に伴う勤務免除及び有給の保障
派遣元事業主は、派遣労働者にも、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の慶弔休暇の付与並びに健康診断に伴う勤務免除及び有給の保障を行わなければなりません。
例32(均衡待遇の例…出勤日数が同じ場合と違いがある場合)
元は、先で雇用される通常の労働者であるXと同様の出勤日が設定されているYに対して、先がXに付与するのと同様に慶弔休暇を付与していますが、先に派遣されている派遣労働者であって週2日の勤務であるWに対しては、勤務日の振替での対応を基本としつつ、振替が困難な場合のみ慶弔休暇を付与しています。
(筆者コメント:慶弔休暇制度の目的を考えると派遣労働者にも原則として同一の付与を認めるべきです。ただし、週所定労働日数が少ない労働者において、勤務日を振り替えることにより慶事や弔事に対応できる場合には、振替での対応を基本としつつ、振替が困難な場合にのみ慶弔休暇を付与することとしても不合理とはいえないと考えます。)
★例33(問題がある場合)
元は、先で雇用される通常の労働者であるXと同様の出勤日が設定されているYに対して、先がXに付与している慶弔休暇を付与していません。
⑲病気休職
派遣元事業主は、派遣労働者(期間の定めのある労働者派遣に係る派遣労働者である場合を除く。)には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の病気休職の取得を認めなければなりません。また期間の定めのある労働者派遣に係る派遣労働者にも、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの期間を踏まえて、病気休職の取得を認めなければなりません。
例34(均等待遇の例)
元においては、先における派遣就業期間が1年である派遣労働者であるYについて、病気休職の期間は当該派遣就業の期間が終了する日までとしています。
⑳法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除く)であって、勤続期間(派遣労働者にあっては、当該派遣先における就業期間)に応じて取得を認めているもの
法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除く。慶弔休暇については⑱を参照。)であって、派遣先及び派遣元事業主が、勤続期間(派遣労働者にあっては、当該派遣先における就業期間。)に応じて取得を認めているものについて、派遣元事業主は、当該派遣先に雇用される通常の労働者と同一の勤続期間である派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除く。慶弔休暇については⑱を参照。)を付与しなければなりません。なお、当該派遣先において期間の定めのある労働者派遣契約を更新している場合には、当初の派遣就業の開始時から通算して就業期間を評価することを要します。
例35(均衡待遇の例…所定労働時間に違いがある場合)
先においては、長期勤続者を対象とするリフレッシュ休暇について、業務に従事した時間全体を通じた貢献に対する報償という趣旨で付与していることから、通常の労働者であるXに対し、勤続10年で3日、20年で5日、30年で7日の休暇を付与しています。元は、Xより所定労働時間の短い(例えばXの半分)派遣労働者であるYに対し、所定労働時間に比例した日数を付与(勤続10年で1.5日、20年で2.5日、30年で3.5日)しています。
(筆者コメント:リフレッシュ休暇制度の目的を考えると、勤続してきた期間と所定労働時間の両方を考慮して、所定労働時間に比例した日数を付与することとしても不合理とはいえないと考えます。)
㉑教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施するもの
教育訓練であって、派遣先が現在の業務の遂行に必要な能力を付与するために実施するものについて、派遣先は派遣元事業主からの求めに応じ、その雇用する通常の労働者と業務の内容が同一である派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の教育訓練を実施する等必要な措置を講じなければなりません。なお、派遣元事業主についても、労働者派遣法第30条の3(不合理な待遇の禁止等)の規定に基づく義務を免れるものではありません。
また、派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間で業務の内容に一定の相違がある場合においては、派遣元事業主は、派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情の相違に応じた教育訓練を実施しなければなりません。
なお、労働者派遣法第30条の2(段階的かつ体系的な教育訓練等)第1項の規定に基づき、派遣元事業主は、派遣労働者に対し、段階的かつ体系的な教育訓練を実施しなければなりません。
㉒安全管理に関する措置又は給付
派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の業務環境に置かれている派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の安全管理に関する措置及び給付をしなければなりません。
なお、派遣先及び派遣元事業主は、労働者派遣法第45条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)等の規定に基づき、派遣労働者の安全と健康を確保するための義務を履行しなければなりません。