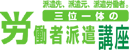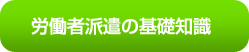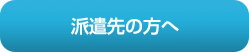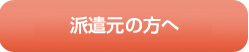第2 労働者派遣事業の許可制への一本化
1 概要
届出制による特定労働者派遣事業が廃止され、労働者派遣事業は全て新たな許可基準に基づく許可制となりました(派遣法第5条1項)。但し、3年間の経過措置が設けられています。
2 改正前の制度
労働者派遣事業は、(1)届出制による特定労働者派遣事業と(2)許可制による一般労働者派遣事業の2つに分かれていました。
上記(1)は「常時雇用される労働者」(注)のみを派遣する事業で、上記(2)は、それ以外の労働者も派遣する事業です。
注:「常時雇用される労働者」とは、雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者(派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者又は1年を超えて雇用される見込みのある有期雇用の派遣労働者)です。
3 すべて許可制に
特定労働者派遣事業と偽って一般労働者派遣事業を実施しているなどの悪質な法違反をなす事業者が見られたこと等から、特定労働者派遣事業は廃止され、労働者派遣事業は全て許可制となりました。
4 新たな許可基準として追加されたもの
派遣元は労働者派遣事業の許可を受けるために一定の基準を満たすことが必要です(派遣法第7条)。改正法は、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、次の(1)~(6)の許可基準を追加しました。
(1) 厚生労働大臣が定める基準を満たす派遣労働者の「キャリア形成支援制度」(後記第4参照)を有すること。
(2) 教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること。
(3) 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約の終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。
(4) 労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う旨の規定があること。
(5) 派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備していること。
(6) 雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、都道府県労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと。
また改正前からの許可基準のひとつである、「事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること」とは、具体的には、資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が「2000万円×事業所数」以上、現預金額が「1500万円×事業所数」以上であることが要件となっています。改正法は、この資産要件について、小規模派遣元事業主の特例として、次のア・イの暫定的配慮措置を付加しました。
ア 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主について、当分の間、基準資産額1000万円、現預金額800万円とすること。
イ 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主について、平成30年9月29日までの間、基準資産額500万円、現預金額400万円とすること。
5 経過措置
改正法施行時点において、特定労働者派遣事業を行っている派遣元事業主については、改正法の施行日(平成27年9月30日)より3年間(平成30年9月29日まで)は、許可を取得することなく、常時雇用する派遣労働者に係る労働者派遣事業の運営が可能です。
また、特定労働者派遣事業を行っている事業主は、経過措置期間において、キャリア形成支援制度の実施等、法により義務付けられている事項については、労働者派遣事業を実施する事業主と同様の実施義務が課せられます。また経過措置期間の経過後は、厚生労働大臣から労働者派遣事業の許可を受けなければ、労働者派遣事業を行うことはできません。